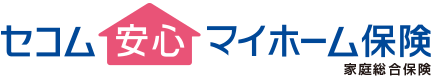ここから本文になります。
- セコム損保の火災保険HOME
- 補償内容
- 地震保険
地震保険
地震の多い日本だからこそ備えは万全に。地震保険をおすすめします。
- ※2022年10月 地震保険改定のご案内(812KB)
- ※2021年1月 地震保険改定のご案内(742KB)
- ※2019年1月 地震保険改定のご案内(584KB)
- ※2017年1月 地震保険改定のご案内(567KB)
- ※2014年7月 地震保険改定のご案内(149KB)
地震保険の必要性について
ご存知ですか?
地震による火災は、火災保険では、補償されません。
| 火災の原因 | 火災保険 | 地震保険 |
|---|---|---|
| 地震・噴火またはこれらによる津波 | ×(※) | ○ |
| 上記以外 | ○ | × |
- ※地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
地震に備えるには、地震保険への加入が必要です
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して、保険金をお支払いします。
お支払い例

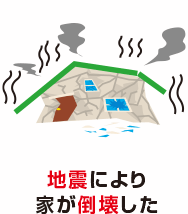
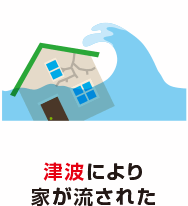
地震保険に加入するには?
地震保険は、単独では契約できません
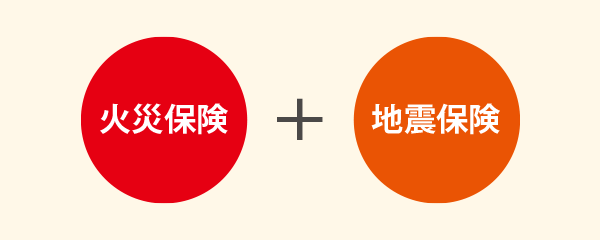
地震保険は、単独では契約できず、火災保険にセットして契約する必要があります。
現在ご契約の火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の中途でも地震保険を契約することができます。
地震保険の対象は、居住用の建物および家財です
地震保険の対象は、居住用の建物および家財です。
ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等(貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品)、明記物件(稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの)には、地震保険をつけられません。
| 保険金額 | 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内
|
|---|---|
保険金額の限度額 |
建物:5,000万円:家財:1,000万円 |
- ※複数世帯が居住する共同住宅建物の場合は、世帯が異なる戸室ごとに5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、分譲マンション等の区分所有建物の場合は、区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
- ※専用店舗・事務所などの建物および建物に収容される動産は対象となりません。
ご注意ください
大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、東海地震にかかる地震防災対策強化地域に所在する建物または家財について地震保険のご契約ができないことがありますのでご注意ください。
お支払いする保険金
損害の程度に応じて下表のとおり保険金をお支払いします。
※左右に動かすことで、スライドさせることができます。
| 損害の程度※ | 損害割合 | お支払金額 | |
|---|---|---|---|
| 建物の主要構造部 (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 |
家財の損害額 | ||
| 全損 | 建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 保険の対象である家財の時価額の80%以上となった場合 | 建物・家財それぞれの地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 保険の対象である家財の時価額の60%以上80%未満となった場合 | 建物・家財それぞれの地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 保険の対象である家財の時価額の30%以上60%未満となった場合 | 建物・家財それぞれの地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水)もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損に至らないとき | 保険の対象である家財の時価額の10%以上30%未満となった場合 | 建物・家財それぞれの地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
- ※「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定については、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います。
(注)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されます。(2024年10月現在)
地震保険割引制度
所定の確認資料をご提出いただいた場合、住宅の耐震性能に応じて4つの割引が適用されます。
- 建築年割引
- 耐震等級割引
- 耐震診断割引
- 免震建築物割引
割引を適用するためには割引の種類によって、次に記載されている確認資料のコピーをご提出いただきます。
- ※次の①~④の割引を重複して適用することはできません。
- ※当サイトの「オンラインお見積り」では、次の②~④の割引を設定できません。
1建築年割引

昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に適用します。
- 確認資料
-
- 1.「建物登記簿謄本」「建物登記済権利証」「建築確認書」「検査済証」等の公的機関等※1が発行※2する書類
- ※1公的機関等とは国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
- ※2「建築確認申請書」等の公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
- 2.宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」「不動産売買契約書」または「賃貸住宅契約書」
- 3.登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書または建物引渡証明書
(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
- 1.「建物登記簿謄本」「建物登記済権利証」「建築確認書」「検査済証」等の公的機関等※1が発行※2する書類
2耐震等級割引

建物の耐震等級(注)に応じて、建物およびその収容家財について適用します。
(注)法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準。登録住宅性能評価機関が発行する所定の評価書等に記載されているもの。
- 確認資料
-
- 1.品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類※2のうち、耐震等級を証明した書類※3
- 2.「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類※4および「設計内容説明書」など“耐震等級”が確認できる書類
- 3.独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
- ※1登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
- ※2品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。(「品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類」について、以下同様とします。)
- ※3例えば以下の書類が対象となります。
- 品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書
- 耐震性能評価書
- 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
- 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
- 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類
など
- ※4認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。
3耐震診断割引

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容家財について適用します。
- 確認資料
-
- 1.耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号または平成25年国土交通省告示第1061号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類
- 2.耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
4免震建築物割引

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である建物およびその収容家財について適用します。
- 確認資料
-
- 1.品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類※1
- 2.「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類※2および「設計内容説明書」など“免震建築物であること”が確認できる書類
- 3.独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書
- ※1例えば以下の書類が対象となります。
- 品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書
- 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
- 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」
- 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類
など
- ※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。
- ※1例えば以下の書類が対象となります。
既にご加入の火災保険等において上記①~④割引を適用している場合は、次の書類を確認資料とすることができます。
- 確認資料
-
対象建物について、建築年割引、耐震等級割引(およびその耐震等級)、耐震診断割引、免震建築物割引が適用されていることが確認できる「保険証券」「保険契約証」「保険契約継続証」「異動承認書」「満期案内書類」「契約内容確認のお知らせ」または「これらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類もしくは電子データ」※1
- ※1証券番号(契約を特定するための番号)、保険契約者、保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)、建物の所在地・構造、保険金額および発行する保険会社※2の記載があるものをいいます。
- ※2「満期案内書類」「契約内容確認のお知らせ」などを確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。